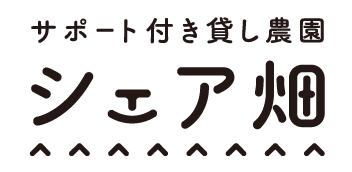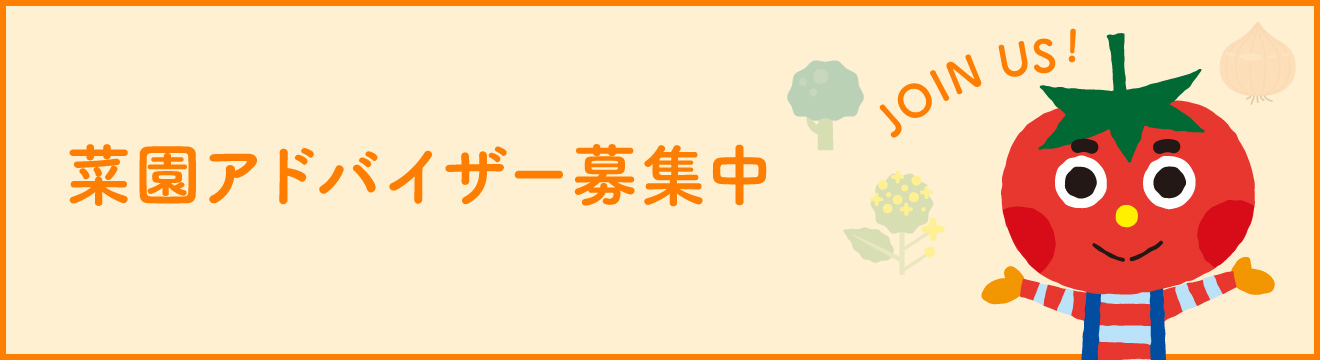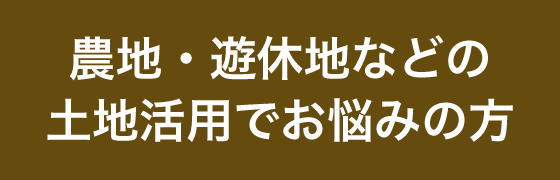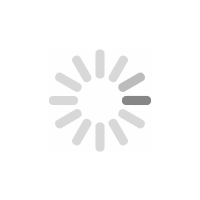貸し農園のブログ

つちのこママの「田畑とつながる子育て日記」vol.2

【入会金50%OFFキャンペーン開催中!】体験もできる農園見学会

『シェア畑キッズ~ジャガイモは増える野菜!?~』2025年秋!募集開始

パパが息子を食育イベントに参加させたワケ
令和を生きるパパ・ママへ 「農」×「子育て」という選択肢

つちのこ母さんの「田畑とつながる子育て日記」vol1
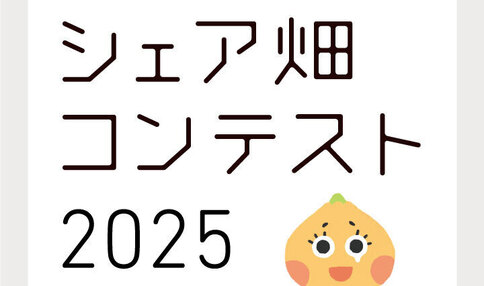
【結果発表】シェア畑コンテスト 2025

東京都練馬区立野町に『シェア畑 吉祥寺北』がNEW OPEN!3月14日(金)より農園見学会開始!

家族一緒に本気で楽しむ野菜づくり|シェア畑利用者インタビュー

茎ブロッコリーの苗を「かわいさ」で選んでみる|ヤスノリさんのシェア畑 vol. 1

プライバシーポリシーの改訂について

今から栽培できる!オススメの秋冬野菜の栽培プランをご紹介!
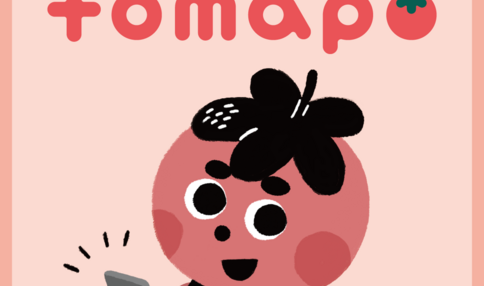
会員向けサービス「tomapo」ってナニ?

育てて食べる喜びこそ食育|シェア畑利用者インタビュー

NHK「おはよう日本」で「広がる貸し農園〜生産緑地の役割〜」というテーマで貸し農園「シェア畑」をご紹介いただきました
近くの畑を探す一覧